栄養士になって、栄養指導を始めたものの、患者が興味をもってくれない
患者の病態を調べて、検査データを見て資料を用意したのに…なんでやろうと思ったことはありませんか。
栄養指導で大切と感じたことを書いてみました。
栄養指導で大切なこと
患者の価値観、バックグラウンドを知ろう
例えば、一般的な高齢男性は「男子厨房に入るべからず」という価値観で生きてこられた方が多いです。患者のバックグラウンドを考えることが大切です。このことは看護における、その人の個別性を考えるうえでも重要な視点でもあります。
初対面の栄養士から、価値観と違うことをいきなり指導をされても、興味を持てなかったり、強制させられていると感じ長続きしなかったり、食事を見直すきっかけにならないということは当たり前かもしれません。
栄養指導は楽しく
自分の栄養指導を振り返ると、栄養士としては正しいことを言っているかもしれないが、それは患者にとって楽しくないこと、つまらないことになっていませんか。検査の数値を追いかけすぎないことも大切です。ご高齢である場合、厳格に数値を守ることが必要か考えましょう。
患者の話を傾聴する
栄養指導という限られた時間の中で、あれも、これも伝えたい!!となる気持ちは分かります。たくさんの情報を一気に伝えられても不安になったり、そこから余計に食事を守ることが嫌になる可能性があります。患者からすると、栄養士の先生は自分の話を聞いてくれないと思っているかもしれません。一度、患者の気持ち、思いに耳を傾けてみましょう。
毎回、反省し次に活かす
栄養指導が終わると、ここをもう少し詳しく説明したらよかったな。もう少し、分かりやすい言葉はないのかな、など様々な反省があると思います。一喜一憂せず、反省を次の栄養指導に活かしましょう。
前回の指導を否定しない
暗黙のルールだと、私は考えています。否定すると、不信感につながりますし、患者が混乱するかもしれません。前任の栄養士も忙しい時間の中、栄養指導を行っていますし、患者の覚え間違いかもしれません。様々な可能性があります。そこは「そういう考えもありますが、、、」などと、伝えることで正しい方向へと導いてあげましょう。
まとめ
私も栄養指導は苦手でした。今は看護師として働いていますが、患者指導では同じことが言えます。その人の個別性を考えて、その人のためにお話しするという感覚でいいかと思います。
日々、精進です。

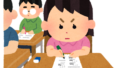
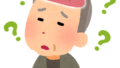
コメント