認知症と聞くと、物覚えが悪くなったり、物忘れがひどくなったりというイメージが浮かぶと思います。
最近、忘れっぽくなったな…
認知症かな?
などと思うこともあるかと思います。
では、認知症とは何かをみていきましょう。
認知症疾患ガイドライン2017
とあります。
ここから読みとれることは
①
「通常、慢性あるいは進行性の脳疾患によって生じ」とあることから、急に発症する病気ではないことが書かれています。ゆっくりと、確実に進行性のある病気です。また脳疾患によって生じるとありますが、脳疾患にも様々な種類があります。治療可能な疾患では慢性硬膜下血腫、血管性認知症、脳腫瘍、正常水頭圧症、ビタミン欠乏症などがあります。難治性疾患には進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、前頭側頭型認知症、進行性白質脳症などがあります。また、その他にもアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症などがあります。
②
「記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断など多数の高次機能障害からなる症候群」とあります。
高次機能とは、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断などの認知過程と行為の感情(情動)を含めた精神(心理)機能を総称します。それら高次機能が障害されることで下記の症状などがみられます。
・物の置き場所を忘れる
・最近の出来事を忘れる、覚えられない
・同じ質問を繰り返す
・集中力がなくぼんやりしている
・ふたつの物事を同時並行でできない
・計画を立てて実行できない
・指示がないと動くことができない
・約束の時間に遅れる
・暴力的、易怒的になる
・自己中心的な行動をとる
また、症候群という言葉があるため、原因となる疾患があって症状が起きるという定義となります。
認知症疾患ガイドライン2010
とあります。
ここから読み取れることは
①
「一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、なった状態をいい」とあります。
一度、正常に達した認知機能ということは、知的障害のある方は含まれないということになります。また、正常に達したということは、その方の過去を知る者にしかわかりませんし、学習能力などは個人差が大きいと考えられます。よって、認知症の方と関わる場合には教育歴を知ることも重要で、例えば漢字を書けなくなったのか、もともと知らない漢字だから書くことができないのかでは大きく意味合いが変わってきます。
②
「脳の障害によって」とあり、例えば脳出血や脳梗塞などが原因となり、脳の部分的な組織が壊れることによって発症します。
③
「それが意識障害のないときにみられる」とあります。意識障害とは、例えば脳出血や脳梗塞などの疾患の症状が無いにもかかわらず、認知機能の低下した状態がみられることを意味します。
まとめ
認知症には定義があり、認知症疾患ガイドラインによって明記されています。ゆっくりと確実に進行し、急には起こらない。また多数の高次機能障害からなる症候群であること。一度、正常に達した認知機能が脳の障害によって持続的に低下することなどを知ることができました。
次は【看護】認知症の診断 ~認知症を知る~です。
限界。
参考文献
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_01.pdf


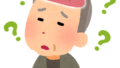
コメント