前回は【看護】認知症の診断 ~認知症を知る~にて認知症は、様々な検査や診察を通して診断されると知りました。
今回は、認知症に至るまでの三段階についてみていこうと思います。
認知症に至るまでの三段階
認知症には三つの段階があります。
①認知症の原因となる疾患
治療可能な疾患
慢性硬膜下血腫、血管性認知症、脳腫瘍、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症(B1、B12、D)など
難治性疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、前頭側頭型認知症、進行性白質症など
中枢神経変性疾患
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症など
②疾患による認知機能障害
例えば、アルツハイマー型認知症であれば記憶障害、ものとられ妄想、取り繕い反応、視空間認知障害など。前頭側頭型認知症では、脱抑制、自発性の低下、無気力、無関心、感情の変化、欠如、常同行動、食行動異常、言語障害など。レビー小体型認知症では記憶以外の認知機能障害、パーキンソンニズム、レム睡眠行動異常症など。血管性認知症では、症状は脳の障害部位に依存する。アルツハイマー型認知症に比べ意欲低下や遂行機能障害が目立つ。脳血流の循環状態の変動に伴い、症状が一過性に改善したり、増悪したりするなど変動がある。人格や感情面は比較的保たれやすい。
③認知機能障害が及ぼす社会生活・日常生活への影響
②で記載した認知機能障害が基盤となり、徘徊、暴言暴力、不穏、攻撃性、易怒性、拒否、無為、拒食、厳格、妄想、不安、抑うつなどの行動・心理症状が出現し、それら症状が、社会生活に影響を及ぼし、日常生活や社会生活を営むことが困難となる場合がある。
ICD-10の認知症の定義、概要、経過、疫学において表のようにある通り

(ICD-10より引用)
日常生活動作や実行機能障害にきたす。また、症状が明らかに6か月以上存在していること
などの文言があり、認知機能障害が及ぼす社会生活・日常生活への影響があることが分かる。
まとめ
認知症には、認知症に至るまでの三つの段階があり、①認知症の原因となる疾患、②認知機能障害(記憶障害、実行機能障害、空間認知障害など…)、③社会生活、日常生活への影響がある。
次回は【認知症・看護】認知症の内訳 ~認知症を知る~について。
限界。

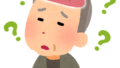

コメント