手術前後や、食事摂取が少ない患者さんに対して医者が輸液をorderすることがありますが、色々な種類がありどういう目的で投与されているのかを知りたいと思ったことはありませんか。
「輸液って何やろう」
僕もわからないことだらけですが、輸液について少しずつ勉強していこうと思います。
体内の水の分布
輸液を知る前に
身体の中の「水の分布」について、知る必要があります。
身体のどこに水が存在してるのかということですね。
体重の約60%は水分です(成人の場合)。その内訳は下記の通りです。
細胞に40%
間質に15%
血管に5%
※間質とは、細胞と血管以外の部分です。
比率として、細胞:間質:血管 = 8:3:1 で存在しているといえます。
ここはしっかり覚えておきましょう!
あれ?でも、教科書では血液は体重の約8%って習ったような、、、と疑問に思った方もおられると思います。
補足として、細胞40%のうち約3%が血管内の、血球(赤血球など)の中にある水分であると考えてください。
なので、循環血液量は
血漿 + 血球 = 5% + 約3% = 約8%
であると考えることが出来ます。
ナトリウムと水の関係
NaとH2Oとの反応性は非常に大きい
中学、高校の理科の授業で習った記憶を、思い出してください、、、笑
化学のカラー教科書で水の中にNaの破片を入れる写真があったと思います。
YouTubeで動画があったので、置いておきます。興味があれば見てください。

Naは血液中でイオン化率が大きい
ナトリウムは水の中では Na+ として存在し、プラスの電荷を帯びています。
水は H2O として存在し、若干マイナスの電荷を帯びています。
そのため、ナトリウムと水はくっつきやすいのです。
プラスマイナスで合体~みたいな
ここで言いたいのは
H2Oを引き付けるのはNaであると覚えてください。
体内のH2O量はNa濃度で調節されるということです。
体液とNa濃度
まずは、この数字を覚えてください泣

輸液の種類
各社によって濃度は若干違いますが、各、輸液のNa濃度です。

次回は、各輸液について書きたいと考えているので、今回はここで終わります。
輸液のキホンの基本なので、数字や、Naは水を引き付けるということを覚えましょう。
次は、輸液のキホン②へ


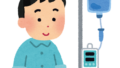
コメント